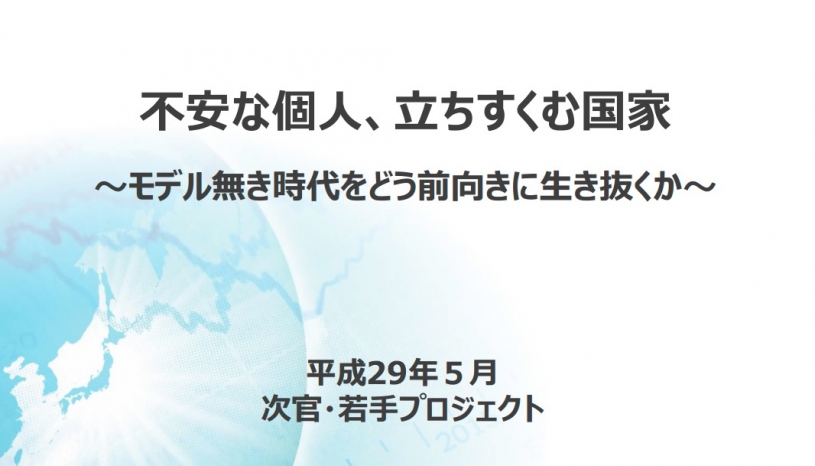5月20日に公開された、経産省の「次官・若手プロジェクト」なるチームがまとめた「不安な個人、立ちすくむ国家 ~モデル無き時代をどう前向きに生き抜くか~」という資料が話題だ。最初にウェブで見かけた反応は好意的なものだったが、次第に反論・批判・不満が噴出するようになっている。そのうち、「言い古されたことばかり」「パワーポイントがインチキ臭い」といった具体的でない批判を除くと、その中でも興味深かったのは以下の議論だろうか。
- 経産省「次官・若手ペーパー」に対する元同僚からの応答 – HIROKIM BLOG / 望月優大の日記
- 「時代遅れのエリートが作ったゴミ」発言者に訊く!若手経産官僚のペーパーに感じた違和感とは。 | 一般社団法人ユースデモクラシー推進機構
- 経産省「次官・若手ペーパー」に対するある一つの「擬似的な批判」をめぐって – HIROKIM BLOG / 望月優大の日記
一連の流れのように挙げているが、両者が直接的に深い論争をしているわけではないので、このエントリでも、どちらが優れているかといったジャッジをするつもりはない。ただ、社会学の立場からこの問題について考えてきた人間としては、「既に言い古されたことばかり」と言われる割に、何が「言い古された」のかをまとめているものが見当たらないことも含め、どこに論点の中心があって、何が対立していて、そして僕たちに示されているのはどのような選択肢なのかということが明らかになっていない点は気になる。そのため、専門家でない人の中には「いいぞどっちももっとやれ」以上の感想を持てないという意見も多そうだ。というわけで、少しばかりの昔話を含めて、問題の構図を読み解いてみたい。
古くて新しい「社会の構造変動」論
まずこの資料が拠って立つのは、1960年代につくられた高度成長期を前提とするシステムが、1980年代生まれにとってはもはや典型的なものでなくなっており、前提から考え直さなければいけないという見方だ。実はこうした見方は「構造変動論」と呼ばれる、文字通り「言い古された」議論である。具体的には、日本においても1970年代ごろから通産省(現在の経産省)を中心に、重厚長大型産業からスモールビジネスへという掛け声があり、何度となく「社会の変化に合わせて産業構造を変えるべきだ」という主張が提示されてきたのだ(この点については、同僚である高原基彰の『現代日本の転機』が非常に詳しく解説している)。
1970年代とは、オイルショックや変動相場制への以降、経済政策におけるケインジアンへの批判などを背景に、いわゆる「戦後の黄金時代」モデルが曲がり角に来たと考えられた時代だった。「新自由主義」と呼ばれる、「政府の縮小によって民間の経済活動を促進する」タイプの政策がまず南米において導入されるのもこの頃で、その理念は1980年代には英米、および日本の一部にも持ち込まれることになった。
ところが1990年代に入ると、こうした「高福祉の大きな政府か、自己責任を重んじる小さな政府か」といった対立に対して、第三極とも言える主張が登場する。アメリカでは、クリントン政権の労働長官を務めることになるロバート・ライシュが『ワーク・オブ・ネーションズ』(1991)を、イギリスではブレア政権のブレーンとして活躍したアンソニー・ギデンズが『左派右派を超えて』(1994)を刊行する。
いずれの著書も、議論の力点は「産業構造の変化がもたらす社会の変化」にある。製造業が中心の社会において典型的なライフコースは、サービス業が産業の中心になる社会においては、様々な点で通用しなくなるのであり、「福祉か自己責任か」ではない、新たな選択肢が必要になるというのだ。
ただし、その選択肢はライシュとギデンズでも微妙に違う。ライシュが強調するのは、サービス業が中心の社会では、高い付加価値を創造する一握りの高度専門職と、感情労働に従事する非熟練対人サービス業(および単純労働者)への二極化が進むということだ。それゆえ政府としては、社会の中流階級を維持することが税収を維持する上でも重要になるのであり、ナショナリズムに基づく教育と社会資本への投資が必要なのだ、というのがライシュの主張だ。それに対してギデンズは、もはや炭鉱町の賑わいを取り戻すのは無理なので、製造業中心の社会モデルから転換できない地域において、市民の自発的活動(彼はこれを「コミュニティ」と呼ぶ)を活発化させ、市民が市民を支えるべきだと主張する。さらに言うと、ギデンズは地域の治安を守るためには、「割れ窓理論」に基づく市民による治安維持が大事だとも述べていて、ライシュの中流階級重視のモデルと比べても、新自由主義的な色彩が濃い。
この違いを産んだのは、ギデンズが社会学者であることと関係している。社会学という学問は、人々が伝統的な共同体を離れ、近代社会の「鉄の檻」に閉じ込められていく流れに対して、人々が自発的に結成する結社や協働社会に期待するという立場をとってきた(この点については、僕の修士論文を下敷きにした『〈反転〉するグローバリゼーション』という小難しい本に少しだけ書いた)。国家ではなく、共同体が人々の生活に責任を持つという発想は、「安全ではあっても国家の縛りの強い福祉」ではない、別のセーフティーネットが社会に必要だという社会学的理念と地続きのものである。
とはいえ、ギデンズのこうした提唱を「新自由主義に妥協した左派」とする見方も少なくなかった。マルクス主義派や労組、あるいは新自由主義を批判するタイプの人々にとって、どのような言葉で飾ろうと、それは国家がなすべき責任をコミュニティに押し付け、またそうしたコミュニティに参加しないものへの排除を容認する議論なのであり、よく言って注意深く見るべき、悪く言うと徹底的に批判されるべきものだったのだ。
日本における混乱
この種の見方をよくまとめたものとしては、渋谷望『魂の労働』、酒井隆史『自由論』など、『現代思想』を中心に活躍した論客たちの著書がある。彼らのおかげもあって日本でも「新自由主義」をめぐる議論が知られるようになるのだが、その後の思想的な議論は、やや袋小路に陥った印象が否めない。先に挙げた高原や、僕の『サブカル・ニッポンの新自由主義』のように、「自由」と「安定」をジレンマ的理念と捉え、「ネオリベに妥協し、安定を脅かす第三の道はけしからん!」と批判するなら、「じゃあ安定のためには国家が個人の生活に介入すべきだということですか」という話になる。他方で、いわゆる「ロスジェネ論争」の論点の一部がそうであったように、「自由な働き方」を推奨することが、「自分で選んだのだから困ったときにも社会が助ける義理はありません」という見放しへとつながったのも確かだ。
そうやって思想的、理念的な議論が拡散する一方、社会的には労働の規制緩和が進み、非正規雇用の範囲が拡大し、しかも経済成長の度合いは諸外国と比べて非常に小さいという「失われた数十年」の時代になる。生活が苦しくなる人々が増えたという実感が広がり、反貧困の社会運動へと注目が集まり、民主党への政権交代につながるも、政権運営の度重なる混乱と失態で政策転換が進まず、今に至るまで根本的な解決には至っていない。
さらに事態を複雑にしているのは、いよいよ日本においても「産業構造の変化を前提にした社会の変化」「社会の変化を前提にした働き方の変化」を本格的に進めようという機運が高まっていることだ。少し考えれば分かることだが、サービス業が社会の中心になるということは、人が休みのときに働く人が増えるということだ。それなのに産業のシステム、教育のシステムが「平日の昼間勤務もしくは専業主婦」の存在を前提に成り立っていると、あらゆることのしわ寄せが働く人に向かう。宅配サービスの再配達やPTAの会議など、ネットでたまにやり玉に挙がる諸々を含め、いざ気づいてみると「いまの生活スタイルとは考え方からそぐわない」ものが、社会の中で無数に維持されている。
社会学的にはこうした齟齬は、すべての生活の基盤を「会社と家族」に依存する前提で構築した結果生じたものだと考えられる。このあたりのシステム的な解説は本田由紀『もじれる社会』に詳しいけれど、要するに、会社の正社員になり、そこで得た給料で買えるものが生活の支えになるという「生活圏の商品化」の状態を変えないまま雇用や家族のあり方が変化すると、そこからこぼれる人が、オルタナティブな手段もないまま、社会的に安全な状態から放り出されてしまうことになるのだ。
ただ問題は、その「社会的に安全な状態」が、どのようなものであるのかについての合意が揺らいでいることだろう。たとえばエスピン=アンデルセンの「福祉レジーム論」における「労働力の脱商品化」という概念を使って考えてみよう。「脱商品化」という言葉が示すのは、お金を払わなくても福祉が得られる、安全な生活を送ることができるという意味だ。だから、「労働力が脱商品化されている」というのは、「働かなくても・働けなくても生きていける度合いが高い」ということになる。それを支えるのは、国家による保障、民間の保険、企業年金、家族の相互扶助といったものだ。日本の場合は国家による保障が手薄で、高度成長期に田舎を出てきた人が多かったため、高齢になって退職した後の生活保障は、もっぱら企業年金と民間のサービスによって担われてきた。
ということは、企業に依存できないことで「社会的に安全な状態」から遠ざけられるリスクが高まるということになる。だが、「安全な状態」を維持するためには、従来型の企業福祉以外にも、「家族が面倒を見るという原則を強化する」とか「早いうちから投資信託などによる資産形成を促す」、「国が基礎所得を保証する」などの選択肢がある。これからの日本におけるセカンドライフの「安全」を守るためにはどのような手段が必要なのか、議論が収束しているとはいえない。
似たようなことは、病気などで働けなくなった人が、あるいは結婚せずに高齢者になった人が、どのように「安全」に暮らせるようになるのがよいか、と考えることもできる。社会学者は、少なくとも現代のシステムが、より「商品化」されたもの、つまり、お金を持っていれば家事サービスや介護サービスを購入することができるが、そうでなければ収入を切り下げてでも血縁者で負担するか、QOLの低い状態で生活するしかない状況になっていることに、批判的な考え方を持っている場合が多い。
問いかけられていたことは何か
もちろん商品化された社会にもよい点はある。お金がなければ何もできない社会は、裏から見れば「お金さえあれば個人の自由が最大限尊重される」社会でもある。よくネットでは「従来の生活を守りながら経済的に小さくなろう」という意見と、「経済的な縮小は弱者の生活から破壊する」という意見が対立するのを見かける。前者の中で目立つのはどうやらシニア世代のようなのだが、その背景にあるのはおそらく「経済的な自立によって得た自由を手放すくらいなら縮小のほうがまし」という価値観だ。
死にそうな目にあっても自由のほうが大事、という価値観は、個人的に表明する分には勝手なのだが、社会全体の人々を巻き込むものとしてはいただけない。とはいえ、商品化された社会を前提に、「誰もが商品市場に参加できるような経済を維持する」というビジョンもあり得るのは確かだ。商品化された生活を十全に送れないのは、まずもって大企業による雇用の流動化、労働者の使い捨てが引き起こした問題なのであり、企業はこれまでと同じように、真面目に働く人は誰でも安定した生活を送れるようにすべきだというのが、従来からの左派の主張だと言えるだろう。
こうした主張に対してあり得る反論が、ライシュやギデンズの唱える「もはや黄金時代の雇用を維持・再建するのは無理」というものだ。単純労働は機械によって効率化される一方で、高付加価値な製品・サービスを生み出すためのアイディアを生み出す力は誰にでも備わっているわけではなく、人々の格差は拡大する傾向にある。さらに言えば、サービス経済の進展も含め、人々の価値観や生活スタイルは多様化する傾向にあり、規格化された人生だけをモデルコースと捉えるこれまでの見方にも大きな問題がある。
そういったわけで、例えば産業構造の変化に代表されるような社会の変化に対応した、新たなポリシーや理念が必要だという話になるのだが、これも一筋縄ではいかない。おそらく大企業の正社員がもっとも恩恵に浴することができる商品化された生活圏のオルタナティブを拡大するという点では、「変化」を求める側の立場は一致するように思えるが、ざっと思いつくだけでも、以下のような立場がある。
(1) 政府は財政を拡大し、従来のセーフティーネットからこぼれる人たちへの手当を拡充すべきだという立場。反緊縮・高福祉という点を考えると、いわゆる「リベラル」や、リフレ派の一部の左派が当てはまるのかもしれない。ちなみに先の大統領選でサンダースの応援に回ったライシュが取るのもこの立場だ。
(2) 政府が財政を拡張するのではなく、民間への規制緩和を通じて、市民が市民を支えあう新たな仕組みの登場に期待すべきだという立場。この中には、シェアリングエコノミーやギグエコノミーと呼ばれる、ネットの仕組みを活用した資源分配、休眠資産の活用、副業の推進などに期待するサイバーアナーキストも含まれる。
(3) 政府は緊縮を進める一方、民間への規制緩和によって企業が自由な活動を行い、その結果として経済成長が進むことでトリクルダウンが起き、人々が商品化された生活に参加できるようにするべきだという立場。格差の縮小よりも、人々の自由と自己責任を重んじるという点で典型的な新自由主義だと言える。
(4) 政府が規制を強化することで大企業への課税を行い、同時に移民の権利などを制限することで、自国民の生活を優先的に支える「大きな政府」を目指す立場。トランプや欧州の一部のポピュリズム政党の立場がこれに当たる。
これらをまとめて論点化すると、以下のようになるだろうか。
A.産業構造の変化に抵抗し、誰もが自由で安定した生活を得られる製造業中心の社会を維持する(従来の左派)
B.産業構造の変化を不可避なものとして受け入れつつ、商品化された生活のオルタナティブを目指す
B-1.財政拡張によるセーフティーネットの拡充を目指すリベラル、リフレ左派
B-2.緊縮と規制緩和を通じて、オルタナティブな市民の支え合いを促すリバタリアン左派、サイバーアナーキスト
B-3.緊縮と規制緩和を通じて、人々の自由と自己責任が重んじられる社会を目指すリバタリアン右派、ネオリベ
B-4.大企業への規制強化と移民の権利制限を通じて、自国民の生活を第一に優先する右派・左派ナショナリスト
上記の区分は、いくつかの変数をひとまとめにした理念型的なものであって、別様の組み合わせもありうる。たとえばトランプの政策はAとB-4の組み合わせだが、他方で規制緩和も行うというものだ。またB-1とB-2を両睨みにする立場もありうるし、議論の火付け役となった経産省の資料では、B-2ともB-3とも読み取れるフシがある。なのでとうてい整理されたものとは言えないのだが、わざわざこういう分類をしたのには理由がある。
今回、発端となった資料に対する反応は、おおむね「AではなくてBであるなんて言い古されたこと」だという前提から出発している。その上でB-1が大事なのにB-3とはけしからん、といった論点が挙がっているように見えるのだ。しかし、「AではなくB」というのは、それほど共有された前提だろうか。
社会全体としてどうか、という点についてデータをもとに考えることも大事なのだけれど、おそらくこの資料に対する最初の賞賛的な反応の理由は、「AではなくB」という主張が明確に打ち出されたことにあったのだと思う。最近のネットの利用者の中心はミドル世代らしいのだけど、昭和の製造業ホワイトカラーモデルを前提にした社会の仕組みの前で戸惑い、様々な負担を強いられるこの世代にとっては、「いまとは別の資源配分が必要なのだ」という言葉こそが求められていたものなのだと思う。
不透明な選択肢と不明瞭な論点
その点で、僕はこの資料に対して「議論の入口」としては非常に使いやすいという印象をもった。というのも、「AではなくB」が通じない人々は、学生であってもまだまだ多いというのが地方私大に勤める現場の感覚だからだ。さらに、流動化、家族モデルの変化、高齢化、メディアの信頼性など、社会学部であればどれも必ず触れるような論点が盛り込まれていることも、その理由のひとつだ。
一方で、そうした社会学に共感的な人間だからこそ感じる限界もある。単純に、これだけのページ数を割いても、「混ぜて論じてはいけないものを一緒くたにしている」「総花的な話になりすぎて具体的な選択肢や論点が見えない」という、社会学にありがちな弱点を晒しているからだ。特に僕が扱う「理論社会学」という社会思想にも近い分野で、こういう問題は生じがちだ。政策論に落とし込むなら、もう少し明快なエビデンスと具体的な選択肢が必要だっただろうとも思う。
しかしながら、議論が続けられることには大きな意味がある。言い古されていようと新自由主義的だろうと、そもそも状況は改善しておらず、というか失業率がほぼ完全雇用レベルにまで下がったことで、経済成長によるパイの拡大より、働き方を含めたライフスタイルの変化や、それを促す仕組みづくりがなければ「この先」が見通せない状態になっている。そのとき、「じゃあどうするの」の先に、「今までと同じようにさせろ」以外にどんな選択肢を描くのかは、どのような立場であれ求められることなのではないか。
NHK出版
売り上げランキング: 359,677
ダイヤモンド社
売り上げランキング: 49,365
而立書房
売り上げランキング: 859,228
NTT出版 (2015-12-18)
売り上げランキング: 295,766
筑摩書房
売り上げランキング: 380,193
筑摩書房
売り上げランキング: 70,109
ミネルヴァ書房
売り上げランキング: 74,642