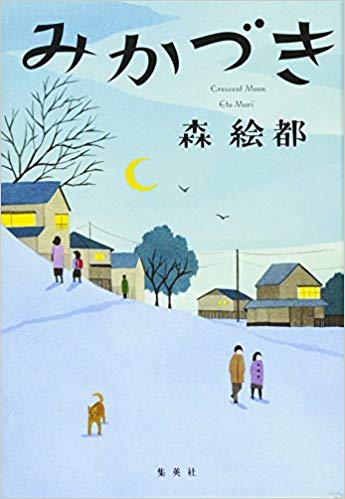森絵都『みかづき』を読了。Kindle Paperwhiteを買ってからというもの、昨年末から続いている文芸ブームに火がついたか、とりあえずこの数年で話題になった作品を片っ端から試し読みして、気に入った作品を通勤中に読んでいる。本作は学習塾と教育がテーマということで、どうも今月はそういう作品に縁があるようだけれど、気に入ったのはどちらかというと文体、そして昭和から平成へと至る時代背景の書き込みだ。
長い作品ではあるものの、それだけの時代の移り変わりと、3世代、4世代にわたる登場人物たちのエピソードを詰め込めば、いきおい展開は早くなるし、それだけ文芸作品としてのディテールは粗くなる。登場人物たちの心の葛藤が、時代の変化に押し流されるように有耶無耶にされていく描写が多く、読み手の心が追いつかない。この辺も「朝ドラっぽい」と評される所以なのだろうと思う。
ただ、本作を「登場人物たちの心の機微をとらえる作品」ではなく、「教育を巡る社会の変化を、架空の家族を通じて描く作品」だと捉えれば、その意義はがぜん高いものになる。学習塾に通うことが世間から後ろ指をさされた時代に塾を創業した昭和、受験戦争が激しさを増す中で、塾経営がビジネス化していったバブル期、格差が拡大するなかで、教育のあり方が問われ直した平成後期。その大きな流れを「家族の物語」として串刺しにすることで、「戦後日本の教育とは何だったのか」を、実感を持って読める作品になっている。なんなら、それぞれのエピソードの背景について社会学的な解説を入れたいくらいだ、と思って巻末の参考文献を見たら、しっかり師匠の本が挙がっていた。かなわないなあ。
また、時代の変化だけでなく、その中で教育が負っている責任や、変わることのない手応え、そしてそれゆえに教育という仕事がもつ「怖さ」について多面的に描かれるのも、本作の注目すべき点だろう。評論であれば、こうしたモチーフの拡散は「著者の主張がぼやける」として避けられるけれど、文芸作品であれば、複数の人物の視点を通して、現実を多面的に描くことができる。タイトルである三日月が、実際にはひとつの丸い月の光と影の面によって構成されているように教育のポジティブな側面とネガティブな側面は互いに同居しながら、そのバランスをときどきによって変え、満ち欠けを繰り返している。それが本作を通して読むとよく伝わってくる。
人にものを教えるとき、そこで大事なのは、「教え方のスキルを高めること」ではなく「教わる側に、教えを受け取るだけのキャパシティを用意すること」だったりする。受け止められるだけのキャパシティのないことを、人は教わることがない。文芸作品も同じで、これだけの情報量を詰め込むと、それを全体として受け止めるには相応のキャパシティがいるだろう。だからこそ、本作を読む人は、その全体像を捉えるために、自分のキャパシティを広げる機会にしてもらえたらと思った。